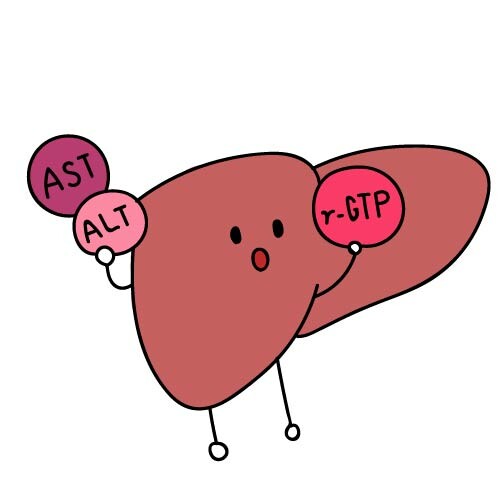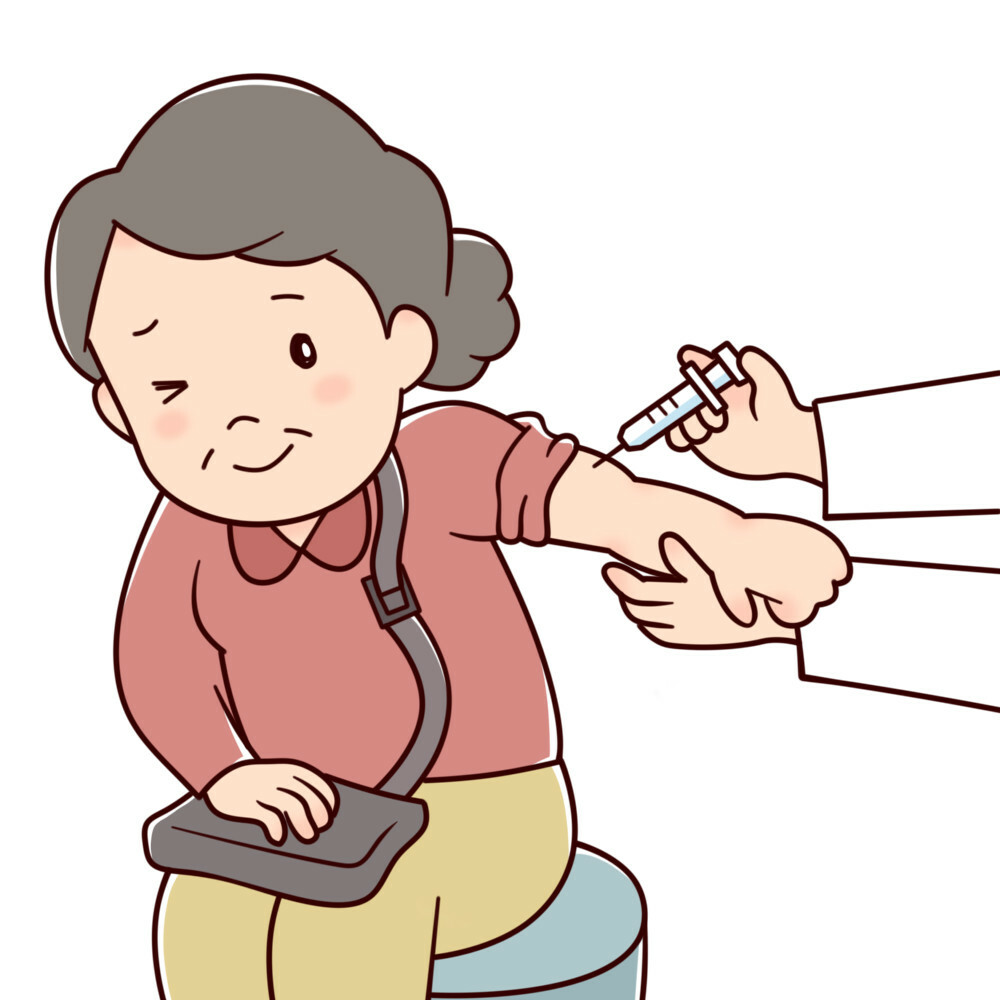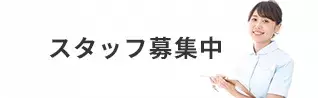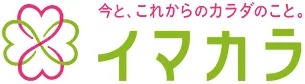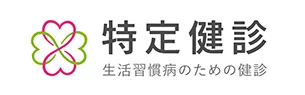コラムColumn

9月になってもまだまだ暑い日が続くようで、引き続き熱中症対策が必要ですね。
長時間の屋外業務や部活動により、若い方が体調不良で来院されることはしばしばですが、高齢者の場合は、比較的短時間の庭作業や畑仕事、買い物程度でも熱中症と思われる症状を訴えて来院されることがあります。
高齢者ではより熱中症のリスクが高いため注意が必要なのです。
そこで今回は、高齢者が熱中症になりやすい理由と対策についてお話したいと思います。
熱中症とは
人間の身体は、通常、体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで熱が外へ逃げる仕組みとなっており、体温調整が自然と行われます。
熱中症とは、高温多湿な環境でその調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもることで生じる様々な症状の総称をいいます。
発症初期には発熱、めまい、吐き気、頭痛、倦怠感などが起こり、重症化すると意識障害や臓器不全を引き起こす危険があります。

では高齢者は何故熱中症になりやすいのでしょう。
以下のような理由が挙げられます。
1. 体温調節機能の低下
高齢になると自律神経や皮膚の働きが衰え、発汗や血管拡張といった体温調節機能が弱まります。そのため、身体に熱がこもりやすく、外気温の変化に対応しづらくなります。
2. 喉の渇きに気づきにくい
加齢とともに「口渇中枢」の感受性が低下し、実際には脱水が進んでいても喉の渇きを感じにくくなります。
3. 筋肉量の減少による水分保持力の低下
筋肉は体内の「水分貯蔵庫」の役割を担っています。高齢者では筋肉量が減少しているため。体内の水分量そのものが少なく、脱水に陥りやすい状態となっています。
4. 基礎疾患や服薬の影響
高齢者では高血圧や心疾患、糖尿病などの慢性疾患を持つ人が多く、利尿剤などの服薬により、体内の水分が失われやすい状況にあります。
5. 環境や生活習慣の影響
高齢者は冷房が身体に悪いと考えて使用を控えることがあります。また一人暮らしや高齢世帯では室温の温度管理が不十分になりやすく、本人が気づかないうちに高温環境にさらされていることがあります。
高齢者の熱中症予防策
1. こまめな水分・塩分補給
・喉が渇く前に定期的に水分を摂る習慣をつける。
・利尿薬を服用している方は、主治医に飲水量の目安を確認しておく。
2. 室温・湿度の管理
・冷房は28度以下を目安にして、湿度も60%以下に保つようにする。
・扇風機などで部屋の空気を循環させる。
3. 服装や環境の工夫
・通気性の良い綿や麻の衣類を選ぶ。
・外出時は帽子の着用や日傘の使用を心がける。
4. 見守りと声かけ
・周りの人がこまめに体調を気にかけて、予防策を促す。
5. 日常生活での注意
・外出は午前中や夕方の涼しい時間にする。
・食事では水分の多い野菜や果物を摂るようにする。
まとめ
高齢者が熱中症になりやすいのは、体温調整能力、口渇感の自覚、筋肉量の低下に加え、基礎疾患や生活習慣などの環境要因が重なるためです。
熱中症は対応が遅れると、時には生命に危険が及ぶこともあります。
重症化を防ぐためにも、水分・塩分補給や冷房の適切な使用を促す周囲の声かけ、見守りが大切です。
心配な場合は、早めに医療機関にご相談ください。