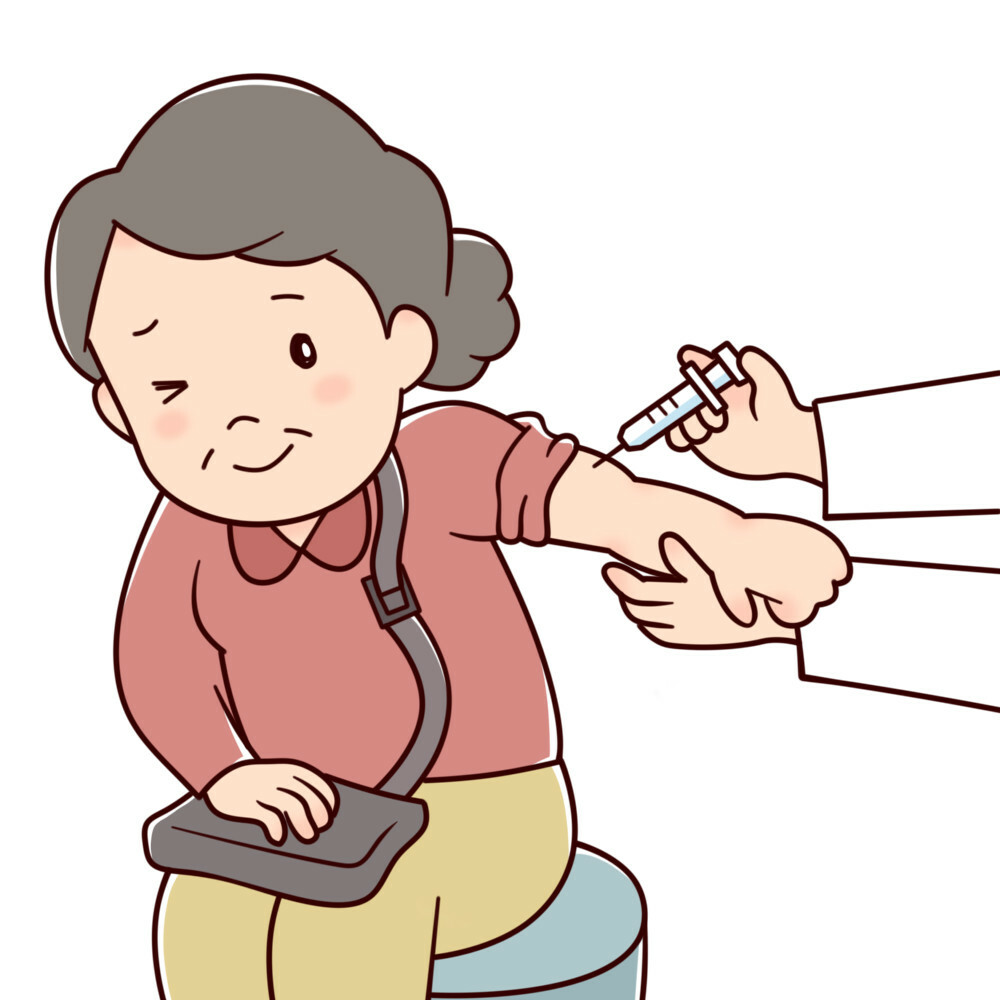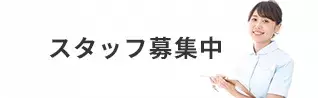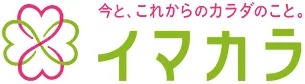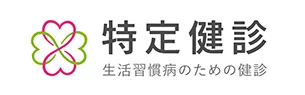コラムColumn

インフルエンザの流行は収束してきていますが、2月に入ってから胃腸炎の方が非常に多くなっています。実際に春日井市の小学校では胃腸炎による集団感染で、学級閉鎖も報告されています。胃腸炎は一般的には高温多湿となる夏季には細菌性、冬から春にかけてはウイルス性が多くみられ、おそらく現在流行している胃腸炎の方の大半が、ウイルス性であると考えられます。
原因と症状
原因となるウイルスは、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、アストロウイルス、コロナウイルスなど多岐に渡っています。これらのウイルスは嘔吐物や下痢便などの中に含まれており、ウイルスが付着した手などを介して口の中に運ばれます。また、空気に存在するウイルスを吸い込むことで体内に入り込むこともあります。症状は、主に発熱や下痢、腹痛、悪心、嘔吐などの胃腸症状を認めます。とにかく急に発症することが多いため、最初はかなりつらい症状となります。
代表的な胃腸炎
ノロウイルス胃腸炎
冬季を中心に多発する集団性胃腸炎や食中毒の原因として最も多くみられます。カキなどの二枚貝を生や加熱不十分な状態で食べることで感染し、感染者を介して、人から人へと感染広がることがあります。潜伏期間は12時間から2日で、悪心・嘔吐、下痢が主症状で、発熱は軽度であることが多いです。症状が消失した後も約1週間はウイルスが便に排出されるため、注意が必要です。
ロタウイルス胃腸炎
ロタウイルスは、冬から春にかけて乳幼児嘔吐下痢症の代表的なウイルスです。5歳までにほぼすべての子供が感染するといわれており、重症化することもあるため、現在は定期予防接種が開始されています。大人で感染しても無症状か軽症で経過します。潜伏期間は2-3日で、発熱、腹痛、嘔吐などを伴う激しい下痢が生じ、約1週間持続します。
その他、新型コロナウイルスでも5人に1人ぐらいは腹痛と下痢の消化器症状を訴えるといわれています。ただし、コロナでは、腹部症状以外に咳や喉痛などの上気道症状を伴うことが多いです。
診断
確定診断としてノロウイルスやロタウイルスでは、少量の便を採取して迅速検査を行うことができます。ただし、陰性であっても必ずしも感染を否定できるわけではありません。実際にはまず詳細な問診と症状、経過から原因菌を推定し、治療を開始することがほとんどです。
治療
ウイルス胃腸炎は、一般的には自然治癒傾向が強いため、治療は対症療法が中心となります。
発熱や下痢、嘔吐などで脱水となりやすいため、十分な水分補給が最も重要です。軽症の場合には、冷たい飲み物や油物は避け、お粥など消化に良い食物を摂取して、腸に負担をかけないようにして栄養を補給します。激しい下痢や嘔吐を伴う場合の脱水には、点滴による輸液を行います。発熱や痛みに対しては、解熱鎮痛剤、嘔気に対しては、制吐剤が用いられます。下痢止めは、腸管内容物の停滞時間を延長して、毒素の吸収を助長する可能性があり、原則的には使用しません。
予防
感染性腸炎では、普段から手洗いや消毒を心掛けることが感染予防に重要です。加熱すべき食材はしっかり加熱してから摂取するようにしましょう。調理中は、生ものに触れた手やまな板、包丁を介して生野菜などに菌が付着して感染することもあるので、その都度、手洗いをしっかりしてください。まな板や包丁は台所用洗剤できれいに洗ってすすぎ、85℃以上の熱湯に1分以上さらして消毒しましょう。
ノロウイルスの感染者がいる場合には、家庭内で広げないために感染対策が重要です。ノロウイルスは吐物や糞便に大量のウイルスが含まれ、乾燥すると空気中にウイルスが拡散することもあります。吐物の処理では、使い捨ての手袋やマスクをつけ処理するようにして、トイレの消毒をしっかりしてください。