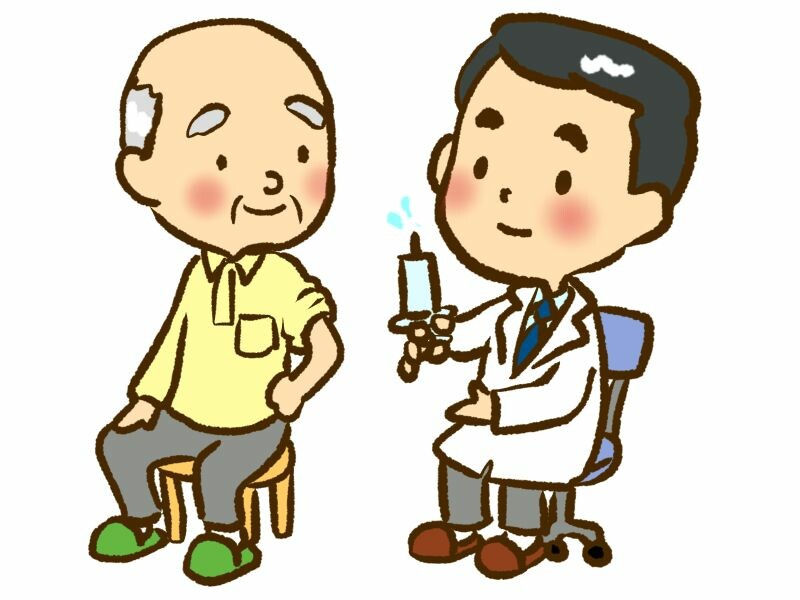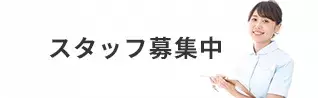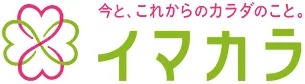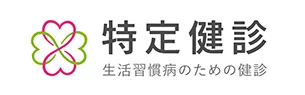コラムColumn

人間ドックのオプションで腫瘍マーカーが項目に入っていると、簡単にがんが分かるなら念のために調べておこうと気軽に検査を希望される方もいると思います。
しかし、いざ腫瘍マーカーが異常値であった場合には、結構心配することになりますよね。
では、健診で腫瘍マーカーを調べることは、どの程度意味があるのでしょうか。
今回は、腫瘍マーカー検査とその臨床的意義についてお話ししたいと思います。
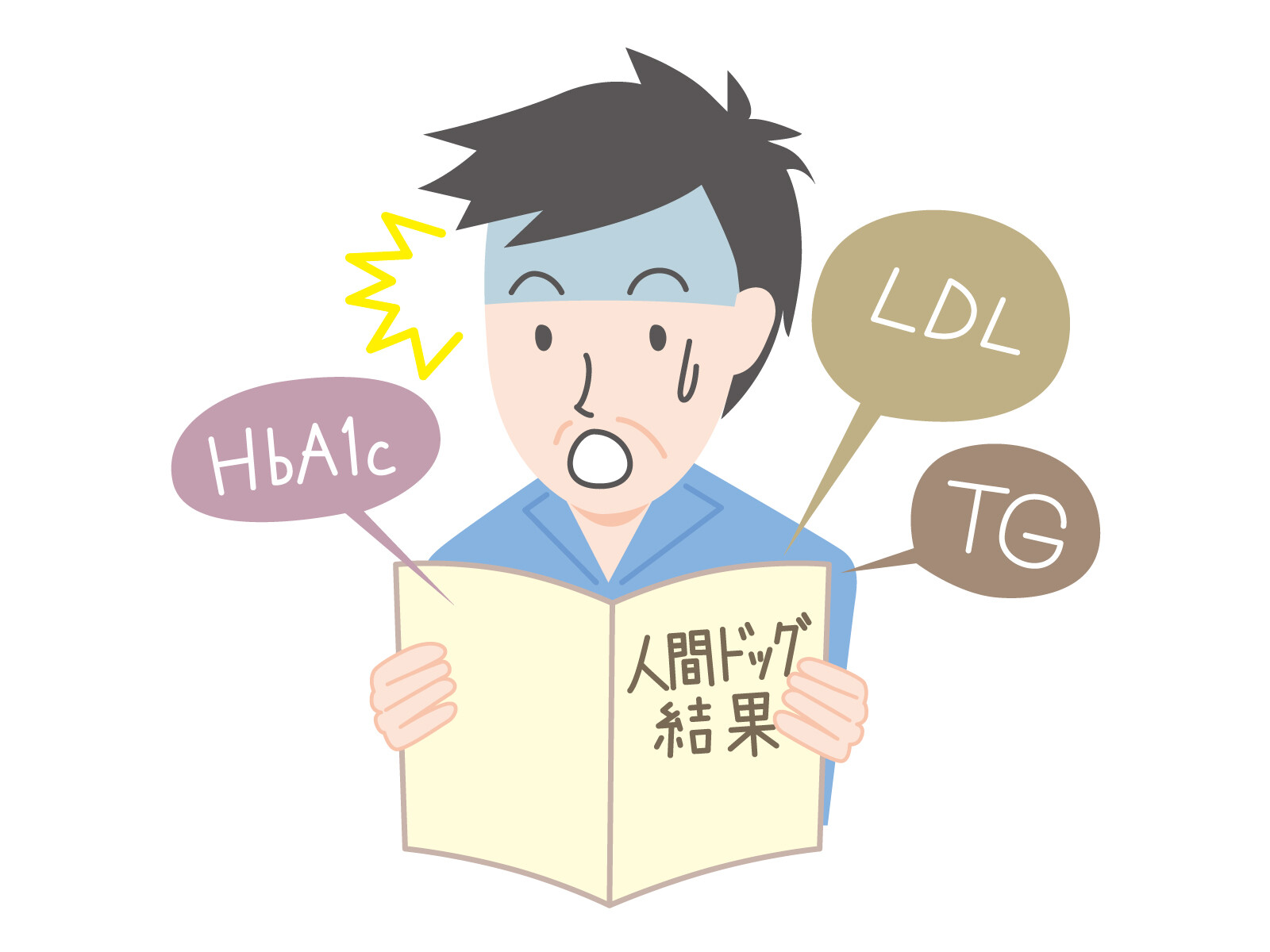
腫瘍マーカーとは
腫瘍マーカーは、がん細胞やがん細胞に反応した周囲の細胞によって作られる特定の分子や物質のことをいいます。
がんの種類によって特徴的ないくつかの腫瘍マーカーが分かっています。
がん細胞の数が増えるほど多量に産生されるので、がんの進行度を数値で評価することができ、腫瘍の経時的な変化を把握しやすいというメリットがあります。
腫瘍マーカー検査の臨床的意義
腫瘍マーカーは、すでにがんになってしまった方に対しての治療効果判定や再発・転移の発見のため積極的に活用されています。
がん細胞の数が多くなると値が高くなりますが、実際にはがんがあるからといって必ずしも異常値になるわけではなく、特に早期のがんでは上がらないことが多いのです。つまり腫瘍マーカーが正常範囲内であっても、それだけで体内にがんがないとは言い切れません。
また、数値が高いからといって必ずしもがんがあるともいえません。肝臓や腎臓の病気、飲酒や喫煙といった生活習慣、薬や炎症性疾患でもしばしば数値が高くなることがあるからです。
したがって、腫瘍マーカー単独でがんを早期発見することは難しく、結局、症状や内視鏡、CT検査、MRI検査など、他の検査結果を組み合わせてがんの有無を判断する必要があります。
主な腫瘍マーカーの種類と陽性率
以下のようにがんの種類によって、いろいろな腫瘍マーカーがあります。
CEA : 大腸がん、胃がん、乳がん、甲状腺がん、肺がん、卵巣がん
陽性率は、大腸がん30-40%、肺がん50%、進行乳がんで50-60%。
CA19-9 : 膵臓がん、胆管がん、胃がん、大腸がん、卵巣がん
陽性率は、膵臓がん70-90%、胆道がん50-80%。
AFP : 肝臓がん
陽性率は、49-71%。
PIVKA-II : 肝臓がん
陽性率は、50-60%。
PSA : 前立腺がん
陽性率は、80%。
CA15-3 : 乳がん、卵巣がん
陽性率は、進行乳がん20-50%、卵巣がん40%。
CA125 : 卵巣がん、子宮がん
陽性率は、卵巣がん80%、子宮頸がん30%以下。
SCC : 食道がん、肺がん、子宮頸がん
陽性率は、食道がん30%、非小細胞癌60%、子宮頸がん28-88%。
CYFRA : 肺がん、食道がん
陽性率は、肺扁平上皮がん60-80%。
陽性率とは、がんがある方で腫瘍マーカーが異常となる確率のことで、がん種によって、腫瘍マーカーの有用性に随分違いがあるのが分かりますよね。
まとめ
腫瘍マーカーは主にはがんの治療効果や再発・転移の判定として用いられ、腫瘍マーカー単独でがんの有無を判断することはできません。
腫瘍マーカー高値をきっかけに、がんが見つかることがないわけではありませんが、その頻度は低く、人間ドックのような健康的な方のスクリーニング検査としては推奨されていないのです。
結局、今のところは個別のがん種に応じたがん検診を受けることが最善であると思われます。